ほとんどの研究において成果を出すには
実験をして結果を出さないといけません。
何か新しい物を測定したり、新しい測定をして
新しい結果が出ることで新発見に繋がるからです。
では、実験をしまくろう!
と、やみくもに実験をしても効率的ではないです。
実験の進め方や実験系を変えることで、かなりの効率化が実施できるので
その方法について述べていきます。
まず、進め方として、
よくあるのが薬品の濃度を変える場合です。
これは、5水準の濃度を振る場合
5水準分薬品をそれぞれ量り取ってそれぞれ溶液を作ろうとする方が多いと思います。
しかし、一番濃度が高い溶液を作って
それを元に薄めて他の水準を作るほうが速くできます。
濃度を薄める場合だと、
一番薄い水準は、一番濃度高い液体少量+多くの溶媒で誤差ができやすいじゃないか!
と反対を受けそうですが、そこは工夫次第でなんとかなります。
一番薄い水準を、3番目に濃度高い液体少量+そこそこの溶媒量
で作製すれば誤差はほぼでないです。
(例えば、1Lの水に濃い溶液1mlを加えた時、
濃い溶液の量が0.1ml多くなっただけで濃度が10%変わります。
1Lの水にそこそこ濃い溶液を10ml加えた時、
濃い溶液の量が0.1ml多くなった程度では濃度は1%程度の誤差で済みます。 )
また、実験内容によるのですが、
ほしい精度に合わせて実験をすべきです。
原子の同位体を観測する、などの
コンマ数%のぶれが結果に大きな影響を及ぼす場合は別ですが
そこまでの精度が必要ない実験が大半だと思います。
その場合は、電子天秤で細かい単位まで測定するよりは
もっと大雑把な秤で量った方が速く済みます。
他に実験が楽な系としては
反応が徐々に進行する系を作ることです。
化学反応率を5%刻みで作ったサンプルを
0~100%まで21水準作ると苦労しますが、
反応が徐々に徐々に進行する系を作って10分置きくらいに測定をすれば楽です。
その測定さえもプログラミングで自動測定プログラムを組んで
10分おきに測定するように設定すればより簡略化出来ます。
測定サンプルを1サンプル準備して
測定のスタートと終わり段階のみに測定に来るだけで済みます。
実験の初めの段階で、
徹底的に楽できる系にするために知恵をひねり出すと
ものすごい楽に成果が出せます。
↓その他、効率的な研究方法は下記本を参考にしてみて下さい。
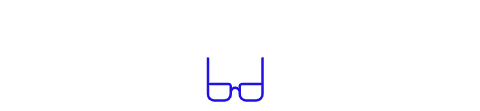

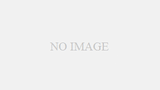
コメント