大学院まででの研究成果で論文5報と学会参加20回の実績となりました。
もちろん、論文は5報とも出版済みで、学会も自分で発表した回数です。
成果が出やすい分野ではあったことは確かですが
それでも同期と比べると圧倒的に成果を出していました。
研究の成果を出す考え方としては
仕事を如何に効率的に進められるか、
仕事を進めやすい環境にするか、
に焦点を絞ってひたすら日々をこなしていました。
参考となるのは過去記事の以下です。
もちろん、研究において成果の数よりも質が大事な場面があります。
しかし、若いうちにおいては数が必要になります。
修士卒の時点で
良い論文1報を持っている人と
そこそこの論文3報持つ人とでは、
後者の方が実力があるとされます。
1報だけだとたまたまだと思われ
3報だと再現性があると思われます。
実際は論文1報目を出すのがしんどく、
1報目の論文書くための基礎知識の習得、
論文化のための英語のお勉強、
基礎実験の実施、
などの時間を多く占めます。
しかし、それさえでれば
以降の論文は、
元々の基礎知識がある状態なので勉強の時間もそこまで必要ではなく
元の研究の派生の研究をすれば
労力としては半分程度になります。
3報目はもっと楽になります。
他には研究室の成果の出やすい環境作りです。
能力がある人は自分の行動だけで成果を出したい欲求に駆られると思いますが
その我を通そうとすると出せる成果に限界が出てきます。
なかなか大学院で研究をする22歳~27歳(博士3年)の間で
その我を通さずに過ごそうと考える人は少ないと思いますが
周りの力を借りたり、周りに貢献したりすることは極めて重要です。
単純な研究能力と同等の重要性と捉えてもらえればと思います。
参考となる記事は以下の記事です。
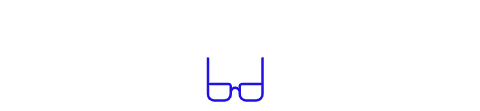

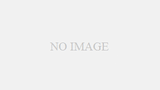

コメント