今回は口頭発表のこつについて書いていきます。
・内容の構成
口頭発表の内容構成はポスター発表と基本的に内容は同じで以下になります。
・研究の背景
・実験手法
・結果、考察
・今後の展望
です。
参考文献はスライドで引用した内容がある度に書きます。
・口頭発表の特徴
内容は同じと言えども、発表形式が異なることで、
発表する時の重みが異なります。
1度の発表で自身の研究室の教授含めて何十人もの人が聞きに来る環境のため
プレッシャーがあります。
下手な発表や下手な質疑応答をすると
教授によってはかなり怒る人もいると思います。
プレッシャーが大きいというデメリット以外ももちろん有り、
自分の研究内容を知ってもらい共同研究につなげること、
自分が将来助教やポスドクとして他の研究室に入れるように
自分の研究と自信をアピールできるメリットもあります。
口頭発表は短時間で多くの人に伝わることが求められるため、
ポスターよりも分かりやすい資料を心掛けましょう。
・資料作り方
まず、スライドを作成したら自分で報告練習をしましょう。
そして、都度修正をしてある程度内容ができたら
スライドの中身を先輩や助教と相談して
ストーリーの分かりやすさ、スライドの分かりやすさ、論理破綻していないか
を見てもらいます。
その後、時間を設けて
必ず先生を含めた研究室メンバーで練習をしましょう。
全体通しの発表をすることで、
再度、先生を含めた状態で
ストーリーの分かりやすさ、スライドの分かりやすさ、論理破綻していないか
を確認してもらいます。
必ず先生には事前に内容は見せましょう。
先生によっては事前のチェックは無くても構わないが
下手な発表をしたら怒るという人もいます。
逆に頻繁にチェックする先生であれば
学会直前の内容の変更は教授に一報いれましょう。
勝手に変更して、先生が口頭発表に参加されて
変更箇所で下手こいたらものすごい怒ります。
怒る・怒られないという、
研究の本筋とは違うことを書いていますが
1回怒られるとその後の研究報告や学会発表が面倒になるので
気を付けましょう(私は前科ありです笑)。
・発表の仕方
発表中は緊張すると思いますが、何回も練習すればなんとかなります。
発表中の原稿読み上げはもちろん無しで、
なるべくスライドは見ずに聴衆を見ながら話すようにしましょう。
発表後は他の人の発表を見ると
スライドや発表方法で良いところが目につくようになるので
きちんと他の人からも学ぶようにしましょう。
発表スライドの資料レイアウト本は下記オススメですので
ご参照ください
・質疑応答のこつ
慣れていないうちはその質問に戸惑って、
だんまりしてしまいがちです。
言っている内容が分からなくとも
質疑応答はただの会話というコミュニケーションだと思って対応しましょう。
質問の言っている意味が不明瞭であれば、
すみません、どういう意図を教えてください?と聞きましょう。
会話でよくわからない質問をされた場合は
もう一度聞き直すなり、どういう意味か聞き返すでしょう。
それと同じで、理解できなかったとしてもプレッシャーを感じる必要は無いです。
それでも自身の知識不足で、言われた質問の内容が不明であれば
後程ご対応させていただきます、よろしいでしょうか?
として済ませましょう。
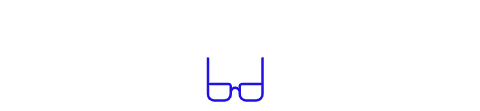
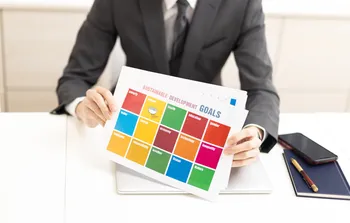
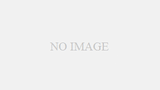
コメント