大学での研究がスタートした時には
先行研究(これまで研究がどこまで進んで来ているのか)のことなど一切分からないです。
過去どこまで研究されて、どこからが新しい領域かを知っているのは
助教や教授のように長く研究に関わっている人達です。
そのため、研究室で行っている最先端の研究テーマの続きや
助教や教授の考案した研究テーマを
メインで実施することになると思います。
助教や教授は過去の蓄積があるため
最新の論文を調べて読むだけで、
過去から最新状況までわかります。
一方、学生にとって、
初めの方は言われた通りに研究をして
意欲的に研究をしたり、運が良かったりで
だんだんと成果を出していき、
学会や論文執筆をすることになっていきます。
そして、学会や論文執筆をする時に
先行研究がどれくらい進んでいるのかを
ようやく調べることになります。
どのようにして先行研究を調べればよいのでしょうか?
調べ方は論文を調べる専用のサイトで確認します。
一般の人も使いやすいのがGoogle Scholar(https://scholar.google.com/)です。
このサイトでは検索して出てくるのがすべて論文、
というサイトです。
ここで自分の研究テーマに関連するワードを入れて調べます。
もちろん、鉄、とかを検索すると膨大な数が出てくるため
鉄 合金 比熱
など、研究に大きく関係している単語を入力します。
今の例では日本語で書いていますが、もちろん論文は英語が一般的なので英語で検索します。
2、3単語程度で打ち、数100~1000程度の検索結果になる程度に絞ります。
そこからはひたすらタイトルをチェックして、
関連しそうな研究をピックアップしていきます。
想像できると思いますが、ものすごく面倒です。
ピックアップする研究テーマは数10~数100個程度が目安です。
その後、ピックアップした論文の研究概要を読んで、
全文読んだほうがよい論文を10~数10程度に絞ります。
だいたい10報くらい全文読めばよいと思っています。
この絞り作業も面倒ですし、
論文10報くらいと書いていますが、
初めのうちは1報読むだけでも苦労するのでこれもまたすごく面倒です。
ここまでしても多少の研究の漏れはありますが、
その10報の論文の中に、自分の研究に大きく関連する箇所に引用文献が引かれていた場合、
その引用文献も確認すれば、先行研究をほとんど網羅して把握できるようになります。
心配であれば、1番初めに検索した、2,3単語を別の単語にして
初めから同じ作業をすればより確実です。
(心配よりもやりたくない気持ちの方が勝るかも知れないですが)
だいたいこの1連の作業
(検索して1000報⇒タイトルチェックで300報絞り⇒アブストチェックで30~50報絞り⇒有益であれば全部読む10報)
を2週間くらいで実施できると思います。
めちゃくちゃ辛いですが、実施すると自信を持って先行研究の部分を説明できるようになります。
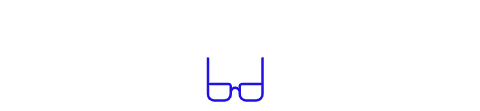


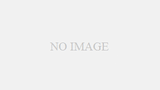
コメント