大学院での研究について学生向けに書いたので
今後は10回程度、助教と教授向けに書いています。
助教授や教授に伝えたいこととしては
自身が管理職であることです。
人によっては、自分は博士課程後の学生の延長で
研究を行うために助教授や教授になったと認識している人もいるかと思いますが
研究室に所属し、そこに学生がいるのであれば
その学生の管理職という立場になります。
よって、主に以下の2点を気を付けることになります。
①きちんと研究をマネジメントすること
②メンタルケアすること
このようなことを書くと
なんでわざわざそこまでしないといけないのか、
自分が学生の頃は放置されていたからする必要を感じない、
管理の無い自由な環境でこそ独創的な研究ができる、
自分のことで手一杯、
などなど
いろいろな想いはあると思いますが
そのような考えは管理者として怠慢だと思います。
大学では、研究を発展させるのが目的だと思うため、
きちんとマネジメントをして研究を進めましょう。
何もせずに学生を放置しているより
マネジメントをするほうが研究が進むことは明白でしょう。
優秀な学生に対して、あれこれ言うのは気が引けるかも知れませんが、
そこは相手の能力に合わせてアドバイスすれば良いでしょう。
組織には
できる人、一般的な人、あまりできない人が
2:6:2の割合でいると言われています。
研究のマネジメントしては
できる人は放置して議論したいことがあれば都度声をかけてもらう、
一般的な人は進捗管理、
できない人は進捗管理に頻度を多くする、
というようなマネジメントをすればよいです。
メンタルのマネジメントとして
できる人ほど指導されていないことが問題になりそうであれば
こまめに声をかけてあげればよいです。
もちろん、一般的な人、できない人も状況を見て声をかければよいでしょう。
メンタルが大丈夫かどうかの確認は
いつも会った時に挨拶をして、
その返ってくる挨拶の声が小さくなっていれば
何かずっと気に病むような悩みがあり得るので詳しく話を聞いてみましょう。
(挨拶は例で、自身のすべての動作に何かしらの付加価値はつけると良いでしょう)
他に、研究を続けていくと飽きが見られることもあるので、
学会後は1日好きな日休んで良い等の、
休みの制度を作ってみても良いでしょう。
内容の重複になりますが
マネジメントは面倒に感じることはあるかも知れませんが、
行ったほうが確実に研究は進展します。
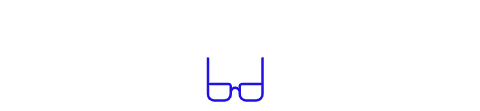

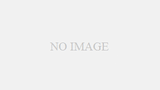
コメント