冒頭
ファラデーの電磁誘導の法則・・・
そう会話に出た瞬間、自分の出番は終わったと思う方が多いと思います。
「電気回路、よくわからない。」
「自分、電気・電子系じゃないし。。。」
そういう風に捉える方はとても多いと思います。
質問してもよくわからない回答が多い、自分って頭が悪いのかなあ
そういう風に感じる方はとても多いと思います。
ただ、実際のところ電気回路を始めから理解できている人って
これまた1/4くらいしかいない気がします。
現状、電気回路についてよくわかっていない人たちが多く日本に集まっております。
ただし、そこで立ち止まっていては、
会社での会議で何も専門的なこと質問できないし、
新しく入ってきた電気系分野卒の新米が何話しているか実際よくわかっていないけど理解している風に振る舞い続けるのも辛いし、
つまるところ仕事に面白みがないので、
どのような教材を使って勉強していけばいいのかレベル順に書いていこうと思います。
レベル0
そもそも、電気のことが分からない場合や
中学校の内容から勉強することをおすすめします。
一般的な人でも意外と知識があやふやだと思うので見てみるべきですね。
自分の本で恐縮ですが、下記の本がお勧めです。
レベル1
直流回路の直列と並列から頭がこんがらがる場合は
前項と同じく直流回路や交流回路の基礎から学びましょう。
直流回路・交流回路を難しくする要因として
交流回路は時間によって電圧・電流値が変わるからで
コンデンサやコイルはその変動による
時間位相がずれの影響を受けるため式がややこしくなります。
直流回路よりも交流回路の方が断然難しく、
高校の物理でも良く分からなかった方も多いと思います。
私も正直よく分かっていませんでした。
いろいろ電気回路を学ぶと、
なんでそうなるのか、と思う箇所がわんさか出てくるのですが、
この段階ではある程度繰り返し演習し、覚えることも必要になります。
理由としては、物理には公理と法則が分かれているからです。
なぜその現象が起こるのかは問題にしておらず(公理)
どのような法則でそれが起こるのかに関して記載している場合が多く、
公理の理由を考えても、そうなるからそうなるとしか答えられない部分が存在します。
例えば、重力がなぜあるのかを考えた時に
物体間には万有引力が働いているから
という答えがありますが
なぜ、万有引力が働いているかはわかっていないです。
物理では
物体間には万有引力が働いているものとして、
ではその力はどの程度か、と調べ、
ロケットなどを飛ばすときに必要な飛び立つときの動力を計算することを目的にします。
交流回路でも、コイルやコンデンサも時間変動して
その理由が不明瞭な個所があると思いますが
まずは、そういうものだとして覚えないと次に進めない部分です。
ある程度の分かりやすい理論説明と、章毎に繰り返しできる演習を備えてある
以下がおすすめです。
レベル2
直流と交流はわかるが、ダイオードやトランジスタになるとわからないレベルです。
電子回路、というと
ダイオードにより整流
トランジスタによる増幅回路
がたびたび出てくるので、
このレベルまでわかっていないと電子回路を見ると分からないことが多く発狂します。
こちらも深く考えずに
ダイオードは順方向だと電流は流れ、逆は流れない
トランジスタはベース-エミッタ間に電流を流すと、大電流を流せる
など、ある程度そのまま覚えた方が良いことがあります。
実際は半導体の根本原理まで理解した方がいいですが、
根本原理が大変難しいです。
このダイオードやトランジスタといった半導体を用いた回路を
半導体回路、電子回路と呼んだりします。
ダイオードやトランジスタの良い解説本はそれぞれ以下です。
市販で売っている本で良いのは以下です。
回路の応用内容を記載した本は以下です。
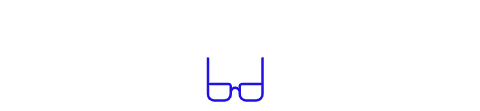
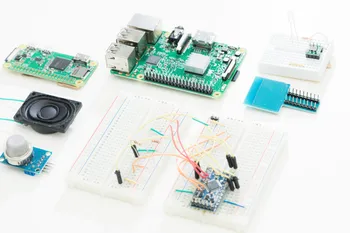


コメント