分かりやすい発表の必要性
大学生は卒業研究論文は表になると、わかりやすいパワポの資料が求められます。
そして、理系の場合は学会に出てわかりやすい資料での発表が求められます。
ちなみに東大は全体的にわかりやすい発表をするのが定評なので
東大に行けばわかりやすい資料になるようによく教育されます。
それで終わりかと思いきや
会社に入ってもわかりやすい資料は求められます。
会社によっては、かなりわかりやすい資料が求められ
大学院時代の高いと思っていたクオリティでも通用しない場合があります。
ここで言う、わかりやすい資料というのは
資料を読むだけで内容が誤解無く伝わるような資料です。
資料作成には2つポイントがあります。
①全体像が入っている
②スライドが1枚1枚、内容を読んでわかるようになっている
①全体像が入っている
①全体像は物事を理解するのに必要で、
人間は全体から見た情報が無いとイライラして理解できないです。
いきなり各論に入るとわからないです。
例えば、外国人の出身を知る場合、
まず、国籍が気になります。
いきなり都市名のような詳細を言われても、
世界的に有名な都市で無いとわからないです。
別の例では
ブロッコリーを食べましょう!
と言われても、は?と思うだけです。
今、肥満な人が多く健康な食事が必要、
ブロッコリーは野菜の中でも群を抜いて栄養価が高い
だからブロッコリーを食べましょう!
という順序でだんだん詳しく説明しないとさっぱり意味不明です。
報告や何かを学ぶ順序も
全体像から学ばないと
何やっているかわからなくなります。
②スライドが1枚1枚、内容を読んでわかるようになっている
これは当たり前のことですが、実際に実践すると難しいです。
自分の中にある程度知識がある状態でスライドを作ると
知識がある前提のスライドになって、
初めて見た人はよくわからないスライドになりがちです。
ここには実際に作ってダメ出しされるという経験もありますが、
わかりやすいスライドというのはある程度法則があります。
以上①、②の詳細を解説している本は以下です。
紹介した本では、著者らが運営しているサイトがあるのでまずはそこを見てもらうと良いでしょう。
伝わるデザインHP:https://tsutawarudesign.com/
こういう見やすいデザインを学んだことが無い人は
中身を見て、いかに自分がデザインに考慮していないかが実感できると思います。
さらにレベルアップとしては、
スライドを”読む”というよりも”見る”というレベルにすることです。
例えば、
新しい設備の立ち上げ
だと読まないといけないですが
新設備立上
とすれば”見る”に近いです。
簡単に言うと、文字数を可能な限り減らすのが”見る”レベルにするのに必要です。
なぜ”見る”レベルにする必要があるのかと言えば
それはスライド発表を聞いて判断する人が、
判断に頭を費やすことに使うように可能な限りするためです。
発表を聞いて判断する人が、
よくわからないごちゃごちゃするスライドを見せられて要領を得ない発表を聞くと
そもそも、何がいいたいのか
という解読に頭を使ってしまうことになります。
そこで理解した後、判断する、というプロセスを経るので
判断者の貴重な時間を費やすことになります。
まともな研究室や企業であれば、判断者は偉い人で、能力が高い人です。
そんな人に、全体を知った上で最適な解を決めてほしいです。
頭のいい人に多くのいろんなことを決めてほしいです。
そうであるならその判断者は時間というのは限られたもので最大限決めてほしいので
無駄な時間は費やさないように下っ端はすべきです。
わかりにくいスライド、わかりにくい発表、
読むスライドだと時間をとってしまいます。
そして、わかりにくいスライド、発表であると
誤解を生んだ状態で判断する可能性もあるので、
改悪のような事態になってしまいかねないです。
読むレベルまでにするスライド作成の参考本は以下です。
いきなりスライドから作るとまずい!といった文書作成の基本も教えてくれます。
資料作成及び報告スキルは会社にいる限り一生使えるスキルなので
投資しても十分元が取れる分野です。
(私はKindle本出版をしていますが、そこでも役に立つスキルです)
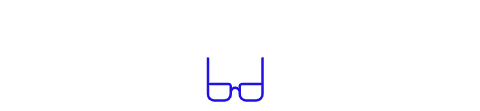



コメント