研究を進めていくにつれて
興味が湧かない時もしばしば出てきます。
というのも一口に研究といっても
・基礎知識を勉強する時間
・英語を用いて論文を読んだり書いたりする時間
・実験をする時間
・パソコンでデータを解析する時間
・人と議論する時間
・研究発表する時間
が存在します。
研究のテーマ自体に興味があっても
記載したすべての状況を楽しいと思いながら、
過ごすことが出来る人は稀です。
その逆も然りで、
研究のテーマに全く興味が無いことに気が付いても
特定の時間は楽しいと感じることがあります。
大学4年生から研究を始めて、(大学によっては2、3年生から研究室に所属するようですが)
さあ、あと3年は研究するぞ!
となっていたかも知れませんが、
研究が覚えていくにつれて
あれ、思っていたのとなんか違う・・・
となっても普通だと思います。
そんなマンネリの対処法として幅広く使えるのが
ストップウォッチを取り出して、
いかに速く作業を終わらせることが出来るのか、自分と競うことです。
作業で無くとも勉強にも使えます。
よし、この専門書を前は10ページ読むのに1時間30分かかったが、
今日は1時間20分だった。
であったり、
この研究作業時間を極限まで工夫することで
始めは2時間かかったが、今では30分でできるようになった。
などです。
研究をしたいから大学院まで行って
やっぱり研究が面白くなかったから研究のやる気が出ない、
ではなく、
どんなことであってもきちんと自分が楽しめるような汎用的な方法を
探し実践するマインドが大切です。
大学院卒業した後、企業に就職する人が大半だと思うので
如何に効率よくするかは大切になってきます。
過去の自分とタイムアタックする遊びは
効率的な働き方の習得でもあります。
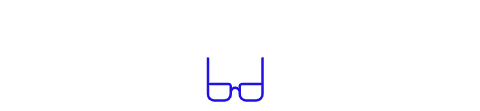

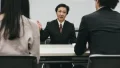
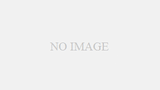
コメント