研究室内で1学年数人いれば、就活へ異様に時間を割く学生が出てきます。
学生としては自分の将来がかかっているので
必死に就活して、それを理由に研究室に全く来ないことがあるかと思います。
指導員の本音としては、
就活に関しての調べ物は土日や平日の帰宅後にやってほしく、
わざわざ平日のほとんどを当たり前のように休んだり、
就活のESを書いたりするのもどうかとは多少感じるはずです。
しかし、それに苛立って
強制的に研究室に来て就活せずに研究するように強いた場合、
いずれ問題になる時代が来ると思うのでやめたほうが良さそうです。
では、どういった対処をすればよいかと言うと、
①学生の就活に割く、情報収集の時間を減らすことです。
②就活自体をしなくて済むようにする(コネで就職先を抑える)
です。
②の就職先を抑えるのは表立って言ってはいけないので、
①のみを説明します。
一部の学生は人生初の就職活動に対して、
不安になる人は安心するまで調べ続けようとします。
そして、説明会も数多く参加するようにして
平日ほとんど就活に時間を当てると思います。
逆に言うと、どの程度まですれば大丈夫なのかを
よく知っている人から必要な量を説明してもらえばよいです。
有効なのはOBを活用することです。
大学院2年の先輩が卒業する前に、
大学院1年の後輩に就活の話をしてもらえば
何をどの程度すればよいのか把握できるようになると思います。
どのくらいの業界を受けたのか
説明会をいくつ受けて、それが周りと比べて多いか少ないかどう感じたのか
面接対策はどのようなことをしたのか
など、うまくいったであろう先輩の就活の話を聞けば
その”うまくいく程度”が分かり
安心して就活に挑めると思います。
また、就活生には就活議事録を作ってもらって、
それを研究室に残すという方法をとれば
後輩の就活もスムーズに行きます。
優秀な学生というのは、自分の力でこれを行った!というのは残したいので
積極的にやってくれるでしょう。
就活する際、多くの学生は
自分が何に向いているか悩むと思いますが、
現在行っている理系の専門分野を選択して選んだのでそこを中心に受けるように言えばよいです。
当人の専門分野は、過去にその専門分野を選んでいるため、
なんだかんだ一番性に合っている可能性は高いです。
もちろん、専門に近い方が内定をもらえる可能性も高いです。
就活を邪魔するのではなく、
就活をさっさと終わらすことが出来る環境にしましょう。
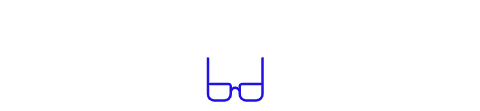



コメント